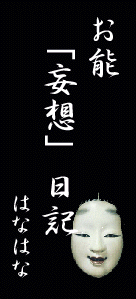
息もつかせぬ舞台であった。 |
||
| ●舞囃子・仕舞について 一曲の能の見どころを取り出して、面や装束、作り物などの舞台装置やワキ・ツレなどの共演者なしに演じる上演形式。 シテ・地謡3〜4人、笛・小鼓・大鼓・太鼓(曲によっては太鼓がない場合もある)によって伴奏し、謡い出しはシテが謡う。 通常は鎮扇(能の場合は閉じきらない「中啓」といわれる扇を使用。鎮扇は一般に扇と言われるものとほぼ同じ形状。 流派によって骨の数や細工が異なる)を使用し、曲によっては長刀、数珠、羯鼓など道具を持つこともある。まれに装束を付ける場合、シテ・ツレ二人(相舞など)の場合もある。 仕舞は、謡とシテのみが演じるもので、舞囃子よりは短い場面になる。 ●切戸など 能舞台は三間四方(5.4メートル×5.4メートル)に橋掛りがつく。「鏡板」といわれる松が描かれた板が背面にはめられている。舞台には4本の柱があり、それぞれ「目付け柱」「脇柱」「笛柱」「シテ柱」と名づけられている。 観客席は「見所(けんしょ)」と呼び、舞台正面を「正面」橋掛かり前は「脇正面」それらに挟まれた三角形のスペースは「中正面」といい、価格が安くなる。(目付け柱のかげになるため観にくい) 幕は橋掛かりにあり、「揚幕(あげまく)」という。 地謡・後見などは舞台向かって右奥の「切戸(きりど)」から出入りする。また舞囃子・仕舞のときは全員が切戸から出入りする。 また、橋掛かりの見所側には松が3本あり、右から「一の松」「二の松」「三の松」。 また松が植えてあるのは「白洲」、また舞台前面には「階(きざはし)」がある。 |
||
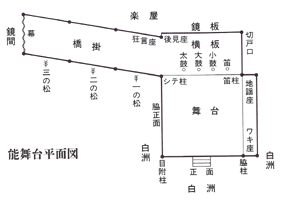 出典: とんぼの本「お能の見方」 白洲正子・吉越立雄著 (新潮社) |
||