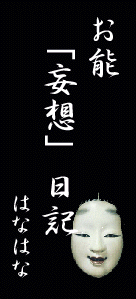
天鼓は鼓が好きだ。鼓の申し子として生まれた彼は、彼しか鳴らせない鼓を愛するがゆえに命を落とした。それでも鼓を召し上げようとし、天鼓を大河へ沈めた皇帝を憎もうとはせず、ただ一筋に鼓を打つことを愛してやまない。その父もまた、皇帝を憎みはしない。 皇帝への庶民の抵抗の話と読むか、芸術賛美の物語と読むか、味方團は、この日、音楽を愛するがゆえに死んだ天鼓の純粋さを全面に押し出して舞った。それもうれしげに楽しげに。 前シテの父・王伯もさらりと演じた。さすがに鼓を鳴らすときには息子への思いが極まるさまをしっとりと見せたが、皇帝への恨みはそれほどには伝わらない。 |
||
| 「天鼓」 あらすじ 天鼓は天から授かった子。天から降ってきた鼓が胎内に入る夢を見て母は天鼓を身ごもり、のちに現実に天から本物の鼓が降ってきて、天鼓が打つと妙なる音を発した。天鼓はことのほか鼓を好み、その音色に人々は酔った。 |
||