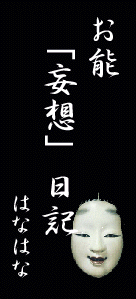
この能のシテ(主人公)はその名の通り「千手の前」という女である。 重衡は、平家の公達ながら早々と源氏に捕らえられて鎌倉に護送されてしまった捕虜の身である。それを慰めようと頼朝は自分の寵愛する千手を差し向けるのである。重衡と美しい千手のやりとりがこの曲の見どころだと思うのだが、どちらも自分の身の上にあきらめと憂いを抱いていること、それが曲の背景を流れているのではないかと思う。 梅田邦久師は名古屋能楽界の重鎮である。何度か舞台を拝見しているが、今回の重衡ほどの色気を感じたことはこれまでなかった。 まったく、芸というのはおそろしいものである。それとわかる演技など何一つないのである。また役者自身の属性(若い、整った顔立ち、体型…)はまったく問題ではないのである。要は、型の中にどこまで埋没し、その型の行き着く先がどんな情感なのか、それを突き詰めているかどうかなのではないのか…。 |
||
| 「千手」 あらすじ 重衡は罪人として鎌倉に囚われている。源平一の谷の合戦では清盛の五男として一軍を率いたのであったが捕虜となり鎌倉へ送られたのであった。その上、重衡は戦の際に南都・奈良の仏閣を焼き討ちした仏敵でもあった。 小書「郢曲之舞(えいぎょくのまい)」ではツレの重衡の嘆きに重点が置かれた演出となり、シテ・千手の登場場面が変わったり一部の詞章が省略されたりする。 |
||
戻る 次へ |
||