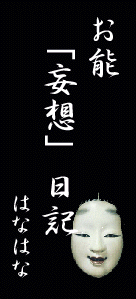
能は「せぬひま」を楽しむものです。何もしていない「間」を味わっていただきたいと思います。 あの所作・この科白・この謡は何を表現している、などの細かい詮索はこの際抜きにして、舞台に登場するものども(人間とは限りません)とともに、見えない風景を見て、それに遊んでいただきたいのです。そのきっかけ・とっかかりとして所作や言葉が存在します。 わかろうとしなくてもよいのです。「ああ綺麗だな」最初はそれだけでいいのです。シテが指し示すその方向に何かがあるのだな、と感じ、それに何らかの情動を感じて舞っているのだな、と思っていただきたいのです。 |
|||
「融」のシテが「月が出た」と語るとき、見ている人は皓々と照る満月を想いうかべるか朧月を想いうかべるか、眼前に広がる風景がちゃんと荒涼とした廃墟かそれとも能楽堂の観客席か、それは見る人の心の豊かさや重ねてきた経験や記憶の質量、感受性に左右されるのです。また、シテ方の技量にも依るかもしれませんが、それだけに見るたびに楽しみが広がる世界ともいえるでしょう。 冒頭に「能楽」という言葉を掲げましたが、これは明治初期に成立した新しい言葉です。能と狂言、両方を含みます。私は「楽」がついたこの言葉が好きですが、最近は「能・狂言」と表記するようです。今回は狂言についてはあまり触れませんが、能は、狂言という「笑い」があって初めて成立する演劇ともいえますので、こちらも機会があればお話ししたいと思っています。 能と狂言は、舞楽や雅楽とともに伝来していた中国・唐時代の雑芸「散楽」に由来するといわれています。軽業や物真似、曲芸、手品や幻術、滑稽や乱舞など、現在の狂言の源流のようなものでした。 それが朝廷の管理を離れて庶民に広まっていったと言われています。院政時代から鎌倉期には寺院の仏事の余興として演じられた「延年」、そのなかの演劇要素の強い「風流」や「連事」、農作業を囃し立てる「田楽」は為政者が庇護し急速に広まります。また寺院に付属し国家安泰を祈る「翁猿楽」も発達しました。 そして室町期には、大和猿楽の四座(外山・とび、宝生、結崎・現在の観世、円満井、金春)、近江猿楽の三座(山階、下坂、比叡)など様々な猿楽座が、田楽に取って代わるようになります。大和猿楽は物真似芸を主とし、近江猿楽は歌舞を重視する芸風を持っていましたが、それらの中から結崎座の観阿弥清次が将軍・足利義満の庇護を得て急速に力をつけ、やがてその息子・世阿弥元清が登場します。世阿弥は物真似の要素をじょじょに減らして、歌舞を中心とした優美な作品を作り始めます。世阿弥は主人公が幽霊となって登場し、二部形式で演じる「複式夢幻能」と呼ばれる構成を大成しました。 戦国期には数多くの大名達が能・狂言を愛好しました。信長が桶狭間の戦いを前に舞ったのは「幸若舞」ですが、彼も能を愛し、自らも舞いました。秀吉は、光秀との戦いや朝鮮出兵を題材とし自作した能を自ら演じています。家康も同様で、やがて能・狂言は幕府の公式演劇「式楽」として保護されます。各大名達もそれぞれにお抱えの役者を持ち、お国入りや婚儀などの慶事の余興や、プライベートな楽しみとして能を楽しんだようです。私の地元・尾張藩においても数多くの演能記録と豪華な装束・面、楽器が残されています。 |
|||
能をどう楽しむか 能にはたくさんの要素が詰まっています。面・装束舞・謡・囃子・舞台装置など、長い年月の中で練り上げ、削ぎ落とされて、洗練されてきた無駄のないモノばかりです。それだけに現代においては、説明不足やある程度の知識を持って見なければ理解できない場合も出てきます。 しかし、それは二の次で良いと思っています。 能を見て、気になることはないでしょうか。 主人公はどんな人となりをしていたのか 能をひとつの拠りどころとして、楽しめるものはたくさんあるのではないでしょうか。それを紹介して行きたいと思います。 |
能面「増女」 少々神がかった若い女性の面。清高な品位があり端整。女神・天女・神仙女など。 多くは天冠をいただく登場人物に多く用いられるため「天冠下」とも称する。 私ご贔屓で師匠である味方團が今まさに面を掛けたところです。(「羽衣支度」) |
||
|
図:とんぼの本「お能の見方」白洲正子・吉越立雄著(新潮社)より
●「鏡板」といわれる松が描かれた板が背面にはめられている。これは「影向
(ようごう)の松」を模したもので、この松を寄りしろに神が下りてくるとされる。 ●舞台には4本の柱があり、それぞれ「目付け柱」「脇柱」「笛柱」「シテ柱」と名づけられている。 ●観客席は「見所(けんしょ)」と呼び、舞台正面を「正面」橋掛かり前は「脇正面」、それらに挟まれた三角形のスペースは「中正面」といい、価格が安くなる。(目付柱のかげになるため観にくい) ●幕は橋掛かりにあり、「揚幕(あげまく)」という。 ●地謡・後見などは舞台向かって右奥の「切戸(きりど)」から出入りする。また舞囃子・仕舞のときは全員が切戸から出入りする。 ●橋掛かりの見所側には松が3本あり、右から「一の松」「二の松」「三の松」。 ●松が植えてあるのは「白洲」、また舞台前面には「階(きざはし)」がある。 ●能舞台ははじめ、屋外にあったもので、京都西本願寺の北舞台(国宝)が形式を残している。 ●能舞台の天井には滑車が、笛柱には丸カンが取り付けられており、「道成寺」において鐘を吊るためだけに用意されている。 ●昔は能舞台の下に大きな壺をいくつも埋めて音響をよくした、と言われている。(現在は埋めている能楽堂は少ない) ●橋掛かりの中央はシテだけが歩むことができる。囃子方も狂言方も能の場合には橋掛かりの左側、奥側を歩く。 ●たとえ能楽師以外でも、また、演能以外であっても、舞台に上がるときは白足袋を着用が大原則。能楽師は足袋ウラで板目を読んでいるとのこと。 ●能を見たあと、拍手をするのが一般的だが、能は余韻を楽しむ向きもあるので、必ずしも拍手はしなくてもよい。特に地謡が「附祝言」を曲の終わりに謡っている場合は遠慮したほうが望ましい。多くの場合、「附祝言」は演目が不幸に終わる場合に舞台を清める意味もあって縁起のよい詞章を選んで謡っているものだからである。 |
|||
|
|
|||

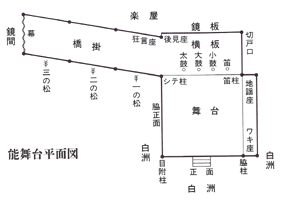 ●能舞台は三間四方(5.4メートル×5.4メートル)に橋掛りがつく。
●能舞台は三間四方(5.4メートル×5.4メートル)に橋掛りがつく。